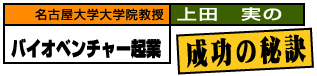
第4回 培養皮膚の臨床応用のもつ矛盾
グリーン教授からいただいたフィーダー細胞の効果は予想以上であった。これまでさまざまなフィーダー細胞を試してみたが、それらをはるかに超える強靭で優れた組織構造をもつ上皮シートが作れるようになった。われわれが培養皮膚の作製と移植をはじめたことをききつけて、近隣の大学病院や熱傷センターから培養皮膚の作製依頼が次第に来るようになった。多いときにはつきに4、5例の依頼があり、研究室のインキュベータは他病院の細胞で一杯になってしまうという事態におちいった。このころから培養を担当していた大学院生からは、ボランテイアで培養皮膚を作ることの不満がでだしてきた。また培養皮膚の作製に要する費用も無視できない額に上ってきた。大学院生の労働コストを加えないとしても、純粋に培養だけに必要な費用は葉書大の培養皮膚1枚の作製に約2万円がかかることがわかった。
こうした外部からの依頼に加えて、名古屋大学内での症例も増え続け、総数で100例を超えたとき、これまでのような一研究室が細々と行うボランテイア的な培養皮膚の供給体制には長期的に見て無理があることに考えがいたった。こうした事態を解決する方法としては3つが考えられた。一番目は日赤の血液センターのように公的機関による培養皮膚の作製と供給を行う方法、二番目は有料で民間の企業が培養皮膚の作製を請け負う方法、そしてこれらが不可能なときには、培養皮膚を使用するごとに患者さんから実費を徴収する方法。
はじめに一番目の方法を試みることにした。名古屋市の保健衛生局や、旧知の議員を通じて県議会に働きかけをおこなったが全くといっていいほど反応はなかった。早々に行政にたよることはあきらめた。また三番目の方法は、国立大学付属病院のような保険医療機関では、培養皮膚の実費徴収は自費診療と保険診療の二本立ての混合診療で一種の違反医療行為になることがわかった。
そして最後にのこされた方法が企業による培養皮膚の作製請負であった。ここでいう細胞培養の請負業は今日でいう再生医療産業の原型となるものであるが、私がこうした培養皮膚の供給体制にしだいに考えが固まっていった背景にはグリーン教授らが設立していた培養皮膚の作製と販売を業とするバイオサーイフィス社の活動があった。この会社はグリーン教授の培養方法を特許化し、ボストンで会社設立をした上で、企業活動を開始していたのである。先に述べたフィーダー細胞の件で、ボストンを訪問した際に、私は同社の社長であり、グリーン教授の共同研究者であったラインハルト博士と面談していたのである。
行政や保険制度にたよらず、医療技術の普及のために、企業を設立して自由に可能性を広げるというやり方に、なにかと規制に縛られ、不自由な思いをしていた私にとって大きな開放感を感じるできごとだった。

▲中央がラインハルト博士
|
<BACK>
|
