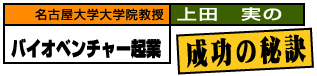
第2回 日本でニュースを知った
本来ならば絶対に助からない二人の少年の命が、「培養皮膚」という新しい技術で助けられた、というニュースは85年のニューイングランド医学誌の発表をうけて、日本のマスコミでも大々的に報道された。当時、名古屋大学大学院で皮膚移植の基礎研究を行っていた、私は新聞報道を通じてオコーナー博士らの仕事を知ったのである。小さな新聞記事であったが、この記事がきっかけになってその後の、私の研究の流れが決まっていったのだから、運命とは不思議なものである。早速、ニューイングランド・ジャーナル誌を探し出し論文を読んだところ、この仕事にはいくつかの画期的な発見が含まれていることがわかった。ひとつは、マウス線維芽細胞の突然変異株である3T3フィーダー細胞をつかって、表皮細胞が重層化したという事実。それまでは正常細胞は重層しないと考えられていた常識を覆したことになる。しかし表皮細胞のうち表皮角化細胞のみが増殖し、ランゲルハンス細胞、メラノサイトなどは含まれていない、いわんや真皮細胞などはないということ。これでは傷が真皮にも及ぶ深い熱傷の患者には対応できないことなどが考えられる。また汗腺、毛嚢などの付属器が含まれていないという、今日培養皮膚の限界として述べられていることは、最初の論文から課題として指摘されていたのである。
ともあれ死の宣告を受けたに等しい、重症の熱傷患者が救命されたという事実は世界中の形成外科医、皮膚科医、関連の研究者に大きな衝撃をあたえた。ボストンから遠く離れた日本の田舎町でこのニュースを知った私もこの新聞記事がきっかけになって、培養皮膚の研究を始めることになったのである。

▲皮膚が増殖する過程
|
ボストン中心部にあるシュライナー熱傷病院に移送された少年たちのわきの下残る2平方センチの皮膚片が採取された。採取された皮膚片はただちにマサチューセッツ工科大学のハワード・グリーン研究室に運ばれ培養皮膚の作製が開始された(写真上)。熱傷の治療は時間との戦いである。培養皮膚が完成するまでに、感染が起きればこどもの命は危機にさらされる。できるだけ早く培養皮膚が完成するよう、昼夜を分かたぬ作業がつづいたことだろう。そして培養皮膚の7回にもわたる移植手術をへて入院20日後に、子供たちの命は救われたのである。
この一連の培養皮膚の移植手術は1985年のニューイングランド医学誌に、二人の担当医であったオコーナー博士とガリコ博士によって報告され、同時にテレビ、ラジオの報道機関に大々的に報じられたのである。これが今日の再生医療の幕開けとなる事件になったのである。
<BACK>
|
