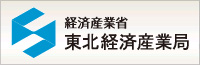�����I�����{�����v��F�O�����O���́w�����v��1960�x�Ɋw��
�@DND���f�B�A�ǂ̏o���ł��B�������߂ăj���[���[�N��K�ꂽ�̂�1987�N3�����{�ŃZ���g�����p�[�N�̖X�͓��Ă��Ă��܂����B���A���������̃p���[�h���t���ĂԂ炵���A�S�Ȃ����s���̕\��Ɋ��C���݂��܂����B�~�ɑς��t��҂����炵���͕č����C�݂̐l�������ς��Ȃ��̂��Ȃ��A�ƁA�G�L�T�C�e�B���O�Ȃ��̊X�ɐe�ߊ�����������̂ł��B
�@���āA���̖K��ŖY�ꂪ�������Ƃ�����܂��B�J�ƊԂ��Ȃ��g�����v�^���[�̐X�̃t�@�T�[�h�ł��Ȃ��A�u�[���̑���œ��키�m�l�̂������̂��Ƃł��Ȃ��B�܂��A�j���[���[�N�E�^�C���Y����1�ʂɗF�l���G�C�Y�ŖS���Ȃ����Ƃ����V���b�L���O�ȃj���[�X��A�q���ނ��̃`���b�g�ň����������l�ގ��̃T�C�o�[�R�b�v�o��Ƃ����L���̂��Ƃł�����܂���B
�@����́A�j���[���[�N�ŕ��������E�I�Ȍ��z�ƁA�O�����O���̌��t�ł��B
�u���z�Ƃ́A���̎��X�̓s���Ŏd����������̂ł͂Ȃ��B�s�s�̖����ɐӔC������v�B
�@���{�l�ŏ��߂ăv���b�J�[�܂���܂��邱�ƂɂȂ����O���搶�ɓ��s���ăj���[���[�N�ɍs���Ă������̎�ރ����ɁA���������c���Ă��܂����B���z�Ƃ������̃v���t�F�b�V�����Ǝ��F���A����������f�I���ꂽ�̂��Ǝv���܂��B�O���搶�Ɛڂ��Ă������́A���̐܁X�ɂԂ₭�悤�Ɍ������ʂ̃��b�Z�[�W���A���܂���ɂȂ��ĂƂĂ����������S���Ă��܂��B
�@�����̒n�A�q���V�}�v��Ō����h�[���a�̃V���{���Ƃ��Ďc�����B���z�Ƃł���Ȃ���A�܂��A�[�o�j�X�g�Ƃ��Đk�Ќ�̊C�O�̓s�s�G���A��������ȂǓs�s�v��ɏ�M���X�������Ƃ͂悭�m���Ă��܂��B
�@���ܐ搶���������Ȃ�A�����{��k�Ђւ̕�����Ă��ǂ��`���Ă݂������낤���B����]�̔��������݂ւ̒Ôg���A�_�ƁA���Y�A�����Ƃ̏W�ςƕ��U�̎�@�A����ɕs���������Ȃ����������G���A�̍Đ��Ȃǂ��������A��k�����ɓs�s����L���čs�������낤���B�搶�Ȃ�A�����ƒn���̑����̊肢���������邽�߂ɒm�b���i��A�C�O������p�m���W�߂āA�N�₩�Ȃ܂ł̃O�����h�f�U�C���ŁA��Вn�̑����̐l�X�Ɋ�]��^���A��[�̖����яオ�点���ɈႢ�Ȃ��B�O���搶��DNA�������p���Ⴋ���z�ƁA�A�[�o�j�X�g�A�f�U�C�i�[��̑n���͂����ۃR���y�Ȃǂ̎�@�ŁA���̓����{�̕����v��ɔ����������Ȃ����̂��낤���B100�N�A����1000�N��̗��j��Y�ɂȂ肤��悤�Ȍv���]�݂����B
�@�]�k�ł����A�O���搶�ɂ͐��X��"�O��"����h�_�܂����B�V���Ђł͒�����"�O����"�Ƃ����ԋL�҂̉���������������ł��B�Љ�s���̃L���b�v�Ƃ̓̂�炶�ŁA2005�N3��22���ɂ��̌����Ȃ܂ł�91�̐��U���I����܂ʼnA�ɗz�ɑ����܂����B30�N�߂��ɂȂ�̂��낤���B�搶�̖S�ҋL���̈����ł́A�V���e�Ђ̗F�l��ʂ��č������Ă��킵�Ȃ��[��������ė����̒��������ɑ����݂����낦�Ă��炢�܂����B���̓����߂����Ċe�Ђ��A���A��A������̎��ӂɒ��荞�݂������Ă�������ł����B

�@���āA���������킯�Ńj���[���[�N�ɓ��s���܂����B���̃v���b�J�[�܂́A�n�C�A�b�g�z�e���`�F�[���̃v���b�J�[�Ƃ�1979�N�ɑn�݂��A�������錚�z�Ƃ̒����疈�N1�`2�l��I�ԍ��ۓI���z�܂ł��B���z�E�̃m�[�x���܂Ɨ_�ꍂ�����c�O�Ȃ��炻��قǂȂ��݂��Ȃ��B���܂ł���ꠕ��F�����������Y���O���搶�ɑ����Ď�܂��A��N�͋���s��21���I���p�ق̐v�ŕ]���ƂȂ������z�Ƃ̖����a������Ɛ��q����܂���Ȃǘb����W�߂܂����B
�@�v���b�J�[�܂Ƃ����Ă������́A�قƂ�ǒm���Ă��Ȃ������̂������͂Ȃ��B�����������f�B�A�̌��z�ɑ���S�́A����߂ė�W�ł�����B���̂��߂��A�O���搶�̎�܂̋g��ɓ��{�����ނɍs�����͎̂������Ńj���[���[�N����[���ɋL���𑗂������A�����͏����������B�t�WTV�j���[���[�N�x�В��݂ŃA�i�E���T�[�A�����I�q�������O�C���^�r���[�����A�j���[���[�N�����̔ԑg�ŕ����������x�ł����B
�@���A���n���f�B�A����́A��ނ̐\�����݂����������B���Ƀj���[�Y�E�E�B�[�N���́A�O���搶��"�����ȋ��l"�Ɛ�^���A���̈̋Ƃ̐��X��傫�����グ�܂����B���ẴW���[�i���Y���̌��z�ւ̊S�̍����ɋ����܂����B����Ȃ��w�̂��ƁA���z�L�҂�ڎw���Ă��������A�Ǝv���悤�ɂȂ�������������܂����B�Y�o�V���̃J���[���ɍ��킹�����ʉ��v�Łu���z�v�̃y�[�W�̃R���Z�v�g�����_�~�[�ł���|���܂����B���z�ʂ�S������̂͂����̂����A����ƕ������Ɉٓ����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�Љ�̕�������������ۂ��A���������Ƃ̔��݂ʼn��������B�u�N�͉�����肽�����v�Ɣ����āA�u�ǂ����ł��c�v�ƌ����ĂЂキ�����B��������Ă��ʔ�����������A�ق�Ƃ��ɁA�ǂ����ł��悩�����B������]�k�ł����B
�@���āA�O���搶�̑��Ղ���i����T��ƁA�����I�����s�b�N�̃V���{���ƂȂ�����X�؍��������������Z��⒴���w�ɑ�\����錚�z�f�U�C���Q�ƁA�s�s�I�f�U�C���̂ӂ��̗��ꂪ����A���̖ڎw���Ƃ���͌�҂̕��ł͂Ȃ��������A�Ǝv���܂��B
�@���̎�܂̌��ߎ�ɂȂ����̂��A1961�N1���ɔ��\�����w�����v��\1960�x�i���̍\�����v�̒�āj�ƌ����܂��B������w���z�w�Ȃ̒O�����O���������肪�������̂ł��B���̔��\���獡�N�ł��傤��50�N�̐ߖڂɂ�����A�O���搶�̃��C�t���[�N���ĂсA�����߂��Ă������ȋC�z�����Ă��܂��B
�@�Ȃ��A���ܒO���搶�́w�����v��x�������A�s�[�����ׂ��Ǝ����v���������͖̂`���ɂ��G��܂������A3�E11�����{��k�Ђ̕����\�z���߂���_�c�ŁA�V�����X�̃O�����h�f�U�C���Ƃ������A�r�W���A���ȓs�s�I�f�U�C���̒�Ăɂ���āA�����{�Ɋ�]�̓����f����悤�ȕ����r�W���������҂��邩��ł��B
�@���f�B�A�̕��݂Ă���ƕ����v��Ƃ����ƁA������{�@��畜�������̎�舵�����肪��荹������Ă��邤���A�����������͂��ߏ��{�R�E�����呍����̒ł��w�E����Ă���悤�Ɂu�P�Ȃ錳�ɖ߂��Ƃ��������ł͂Ȃ������v�Ƃ��Ȃ���A��͂茳�ɖ߂��悤�Ȉ�ۂ������Ă��܂��܂��B��c�⌟���ψ���̍\����L���҂̊�Ԃ�́A�����A�o�ρA���Z�̐��Ƃ������A�����r�W�����Â���ő傢�ɗ͂����Ăق����s�s�v��̐��Ƃ�A�[�o���f�U�C���̃N���G�^�[�̎p�����ڂ�ł��Ȃ����A�ƐS�z���Ă��܂��B
�@���������̐V�����̈�ɓ��ݍ���ł���̂ł�����A������}�`����Ȃ����ꂱ��3D�ɂ��f���ŃC���[�W����������@�����邩������Ȃ��B�G�l���M�b�V���Ȏ�҂̓o��̃`�����X�̏�ɂ��Ă������Ȃ����B�Ȃ������āA�����͎�҂̎蒆�ɂ��邩��ł��B���E�̌��z�ƁA�f�U�C�i�[�ɌĂт����鐢�E�R���y�����{����̂��A�C�f�B�A�ł��傤�B���{�R��Ăł͂Ȃ����A100�N��A1000�N��ɋy�ԁA���S�E���S�A���A�G�l���M�[�A������L�[���[�h�ɂ����u���E�̕����̐�[��������v�Ƃ������ʂ��f���ŗ��̓I�ɕ����яオ�点�Ă��炢�����B
�@���������Ȃ̂ŁA�ǎ҂̊F�l���C�ɂȂ��Ă��邱�Ƃł��傤����A���́w�����v��x�͂ǂ�Ȓ������̂��B�����Љ�܂��傤���B
�@�w�����v��\1960�x(���̍\�����v�̒��)�B
�@���̖ڎ��ɋL���ꂽ��ȍ��ڂ́A�ȉ��̒ʂ�ł��B
�T.1000���s�s�E�����̖{���|���̑��݂̏d�v���E���̔��W�̕K�R���|
�U.1000���s�s�E�����̒n��\���|���S�^�E���ˏ�\���̖����ƌ��E�|
�V.�����v��1960�|���̍\�����v�̒�ā|
�W.���S�\��������^�\���ւ̉��v
�]�T�C�N���E�g�����X�|�[�e�C�V�����̒�ā|
�X.�s�s�E��ʁE���z�̗L�@�I����
�|�R�A�[�V�X�e���ƃs���e�B�ꂷ���̒�ā|
�Y.�s�s�̋�Ԓ����̉�
�|���㕶���Љ�f����s�s��Ԃ̐V���������|
�Z.���݂̃v���O����
�|�����̃G�l���M�[���\�����v�̃G�l���M�[�ɓ]������������̒��
�@�e�͂��Ƃɂ��ꂼ�ꂻ�̃e�[�}�Ɍ��y���A�T�͂ł́A��O���Y�Ƃɑ�����l���̏W���ɂ��1000���s�s�̐��藧������l�����s�s�ɏW�����Ă������o�܂�����܂��B�U�͂ł́A�s�s��ʂɊւ��Ă̂܂Ƃ߂ŁA�u���S�^���ˏ�̌�ʃV�X�e���͌��E�ɂ��Ă���A�s�s�E��ʁE���z��L�@�I�ɓ��ꂷ��V�X�e�����K�v�v�Ƃ��A����Ɂu�����̗����������X�s�[�h�ƃX�P�[���͓s�s�̋�Ԓ�����j����A�V������Ԓ��������ׂ��v�ƌ��͂������N���A���̖{�_�Œ��Ă����܂��B
�@�v��ƁA���S�^�E���ˏ�A���^�E���s�ˏ�V�X�e���ƕ\������̂����A���̕���͓����p��𓌋�����؍X�Â֒�������n�C�E�G�C���́u�s�s���v����{�Ƃ��Ă��܂��B���̃n�C�E�G�C�ɂ��āA�Ғœ����̔w���̐����v���Z�X���ɐ������A�s�s���Ƃ����V�����T�O�����邱�Ƃɂ���āA�����̍\�������S�^���ˏ���^���s�ˏ�ɕϊv���Ă䂭�Ƃ����B�܂�A�s�S�@�\�����͂Ɋg�債�悤�Ƃ���ƁA�����̏Z��n���Ă����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ĐE�Z�ߐڂǂ��납�A�E�Z�������Ȃ�ʋΎ��Ԃ�����ɒ����Ȃ邱�Ƃ��s���ɂȂ�B�����ŁA�����������S�^���ˏ�̏]���^�̃V�X�e�������߂āA�ނ���s�S�̃G�l���M�[�𓌋��p��ɐL���Ă����Ă��̗��T�C�h�ɏZ������ĂĂ����Ƃ��������\�ȓs�s�̃R���Z�v�g���Ă��Ă����̂ł��B
�@�}�ʂ�摜���g���ăr�W���A���ɑi���Ă���ق��A�l���̕ϑJ�⏫���\���A�\�Z�I�ȗ��t�܂ł̏ڍ׃f�[�^�荞�A�Ⴋ�O���搶48�̟Ӑg�̃v���|�[�U���Ƃ����邩������܂���B
�@�搶�̑��Ղ����Ă����ƁA���́w�����v��x�̐��E�I�]���Ƒ��܂��āA�O���搶�ɕ��������̃`�����X�����́A���[�S�X���r�A�A�M�i�����j�}�P�h�j�A���̎�s�A�X�R�s�G�̓s�s�v��ł����B1963�N�ɋN��������n�k�ŃX�R�s�G�͓s�s��7�������A����1100�l�A������4000�l�𐔂����B1966�N����72�N�ɂ����ĒO���搶�𒆐S�Ƃ���`�[���̐v�ɂ��Č����Ƃ��s���A�r���̗������ԋߑ�s�s�ւƐ��܂�ς�����Ƃ����܂��B�}�U�[�E�e���T�����̒��Ő��܂ꂽ�̂͂悭�m���Ă��܂��B
�@�Ƃ���ł��̊X�̕����͍��A��UNDP�i���A�J���v��j�������v��̍��ێw���R���y���s���܂����B�w����6�l�ł��炻���O���Ă�1���ƂȂ����B���̎��A����MoMA�V�ق̐v�Œ��ڂ𗁂т錚�z�Ƃ̒J���g�����A���V���A�n�Ӓ�v���炪���n�X�^�b�t�Ƃ��Ĕh������Ă��܂����B�O���搶������̌��z�w�Ȃ���s�s�H�w�ȂɈڐЂ����̂�1963�N�ŁA���z�Ƃ��s�s�v����ӎ����n�߂�����ł����B
�@���������A�O���搶�̌��_�Ƃ������A�Ȃ�����قǂɓs�s�v�ɂ������̂���T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�X�R�s�G�́A��n�k�œs�S�����قƂ�lj��A�Z���������̕��֏Z�ނ悤�ɂȂ�A���̂��ߓ����Ƀ��j�A�\�i�����I�j�ɒ����L�тĂ������B�s�S���̓s�s�v��͒n���̃`�[���ƘA�g���Č��݂������]�u���z�̑����G���w�X�y�[�X�f�U�C���x91�N5�����v�Əq�ׁA�s�s�v�̏d�v�������������Ă��܂����B
�w�܂�A�����������Ƀ`�����X�����܂��Ă��܂����悢���A���̃`�����X���ƁA�����̂悤�ɉ���Ύ��ɂ����A�����n�k�ɂ����Ă��A���̖؈���ɂȂ��Ă��܂��B�����������I�A�����������������������B��k�ЂƂ�����Ƃ��A�܂������Ă��쌴�ɂȂ��������ł���B�������A���������`�����X���Ƃ炦�ēs�s�̍��i�Â���������ɂ���Ă���郊�[�_�[�����Ȃ��������߂ɁA���̏Ă��Ղɗ�������o���b�N�����Ďn�߂�Ƃ����悤�ȍČ��̎d�������Ă��܂����x
�w����̂��Ƃ́A�o�ϓI�ɂ��j�]���Ă����̂ŕx�̒~�ς��Ȃ������B�����ł��܂��Ȍ��z����낤�Ƃ����b�͑S���łĂ��Ȃ��āA��������o���b�N�����āA���Ƀu���b�N����ɂȂ�A���ꂩ��2�|3���W�܂��ăR���N���[�g����ɂ��悤�Ƃ�����ɁA�����炭���̎p�ɂȂ�܂�3�A4�炢���đւ���Ă���̂ł͂Ȃ����낤���A���̂������������Ă������Ƃ����̂Ńy���V���E�r��������ڂ��ė������ԂƂ����A�����ǂ��ɂł��݂���悤�ȓ����̊X���݂��ł����̂ł���x
�w���̂悤�ɓ����̂ł����Ƃ����̂͂܂��������R�����I�ŁA���H�ЂƂƂ��Ă݂Ă��A�̂̔_�������̂܂c���Ă��āA�Ԃ��ʂ�̂ɋ������班�������L���悤�Ƃ������x�̂��̂ł���B���H�ɂ����Ē����L�т�B�����킢�ߔN���{�̌o�ς���������1�l������ɂ���Ɛ��E��L���ȍ��̒��ԓ���������B�����炿���Ƃ����~�ς��㐢�Ɏc�����ł͂Ȃ����Ƃ����C�����łĂ������A����ł��܂Ƃ܂������Ƃ͉����ł��Ă��Ȃ��̂͂ǂ������킯���낤���x
�@�O���搶�́A���ꂪ���{���̓s�s�̌��݂̎d�����Ƃ�������܂ł����A�����̔��W���l����ƁA�傢�Ɋ뜜�����Ƃ���ł���A�Ƃ����B�܂������̐܂�A�������H�̂킫���W�c�œo���Z���鎙���̗�Ƀ_���v��Ԃ��˂�����ŔߎS�Ȏ��̂����₽�Ȃ����Ƃ�J���āA���̌�̓s�s�v��ł́u�l�ƎԂ̕����v��D�悳���Ă��܂����B�ԎЉ�Ƃ͂����A�W�c�ŗ���Ȃ������̂킫�����ꂷ��ɎԂ������Ȃ����i�������A���[�J��Ԃ���Ă���̂́A�l����Έُ펖�Ԃł��B������Ȗ،������s�]���ɂȂ�������6�l���ɂ܂����B
�@�b��{��ɖ߂��܂��傤�B���̎茳�Ɂw�����v��\1960�x�Ƒ肵�������q�̌��{������܂��B�搶���璼�ځA���������̂ł��B���̕\�����߂���ƁA�����Ɉꕶ���Y�����Ă��܂��B
�w�������́A����Ƃ������ɂ��čl���A�����ɑ��Ē�Ă𑱂��Ă䂫�����Ǝv���Ă��܂��B�i�����j�A�ł��邾���L���A�܂������Ƃ��������A�����̍����������݂̏�J���Ă�������X�ɁA�����ɋ��������ƍl���A�ЂƂ܂��������������q���������Ƃɂ��܂����x�ƌ��A�ȉ��A��_�ȒƂ͗����ɁA���̍s�Ԃɂ͒O���搶�炵���ׂ₩�ȑ��������������܂��B
�@�Ⴆ�A�w���̒�ẮA���Ȃ��̓I�ȑ��������Ă���܂��B����������̓I�ȑ�������ƁA���̌`�ɂ�������āA���̔w����݂悤�Ƃ��Ȃ����Ƃ������N���肪���ł��B�������A�������͂��̑��̔w��ɂ���l������A���@��A�܂��������Ƃ炦�Ē��������Ɩ]��ł���܂��x�Ƃ��̐^�ӂ�`�������ŁA�w���̒�Ă��Ŏ����悤�Ƃ͎v���Ă��܂���B�F�l�̔ᔻ�ɂ���Ă킽���������g�̍l�����C�����Ă䂫�����Ǝv���Ă���܂��B��萳�����l�����ƁA��Ă��Ȃ����A���̒�Ă��ĂĂ��A������x�����邱�ƂɁA�����Ă�Ԃ����ł͂Ȃ��B�������̂����ЂƂ̔O��́A�������~�ς����萳�����������Ă������Ƃɂ���x�ƁA�����ȕ������ł����A�����ł��B
�@����͒̂���Ί����̃��b�Z�[�W�̂悤�Ȃ��̂ł��B�O���搶�̂ӂ���̌��������A���ɓ`����Ă��܂��B���̉��i��1961�N3��1���Ɠ��t������A���̐^���ɂ́A�O�����O���̏����A���̃y�[�W�E��i�ɂ͓���O�����O�������́w���������x�ɉ�������_�J�G���A���V�A�n�Ӓ�v�A����I�́A�N�z���̊w���炪����A�˂Ă���ق��A��c�F�A��J�K�v�����̖��O���U������܂��B
�@�����v��1960�́A���̌�A�����G���A�̗ՊC���s�S�v��ւƓW�J����Ă���̂͂������̒ʂ�ł��B���́w�����v��x�́A�C�O�ł͂܂�������]�������Ă��܂��B����́A�O���搶���肪�����s�s�v��̎傾�������̂ł��B�����������̂�����A�������Ȃ��������̂����邪�A�O���搶�͂����g�̎v���𑶕��ɔ������ꂽ�̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B
�@��k�Ќ�̓s�s��������|�����u�X�R�s�G�s�S���Č��v��v�ɑ����ANew York �́uMaster Plan for Flushing Meadow Sport Park�v�ASan Francisco �́uMaster plan for Yerba Buena Center San Francisco�v�ANepal�́uLumbini Sacred Garden-Birthplace of Buddha Lumbini�v�A�C�^���A�E�J�^�[�j�A�s�́uLibrino New Town Project�v�A�e�w�����́uAbbasabad�@New City Center �v�A�J�^�[���́uHis Highness the Emir's Palace the State of Qatar�v�A�i�C�W�F���A�́uCentral Area of New Federal Capital City �v�A�i�|���́uMaster Plan and Urban Design for The Naples Administration Center�v�A�p���E�C�^���A�L��uGrand Ecran �v�A�����āu�����v��1986�v�Ɛ������B���̃x�[�X�́A��͂�u�����v��1960�v�ɂ��������Ƃ͊m���ł��B
�@�O���搶���������ꂽ�̂��ɔ��\���ꂽ�w�O�����O�@DNA�x�iBRUTUS Casa���ʍ��j�ɂ��ƁA���E�̌��z�Ƃ炪�O���搶������ȕ��ɘ_���Ă��܂����B�����[���̂ŁA�Љ�܂��B
�@�p�����\���郂�_�j�Y�����z�̐��ƁADennis Shap���́A���z�]�_�Ƃ̌̃��C�i�[�E�o�i���������̒����w���K�X�g���N�`���[�x(1976�N)�ŏЉ�����͂����p���A���̓����v��1960�N���u60�N���ʂ��āA���{�⌚�z��s�s�v��̃C���X�s���[�V�������Ƃ��炵�߂�����v�ƕ]�������Ƃ�`���Ȃ���A�u60�N��́A�C�M���X�̃A�[�L�O������C�^���A�̃X�[�p�[�X�^�W�I�Ȃǐ��E�e�n����o�Ă���킯�ł����A�O������͂��̃p�C�I�j�A�ł����v�Əq�ׂĂ��܂����B
�@�|���s�h�D�[�E�Z���^�[�̌��z���f�U�C�������C�L�����^�[�̃t���f���b�N�E�~�Q���\���́u�A�[�o�j�X�g�Ƃ��Ă̒O�������[���b�p�ōŏ��ɔ��\�����̂�1965�N�́A�X�R�s�G�s�S���Č��v��ł����B�ƂĂ������傪����ȃv���W�F�N�g�ŁA����ɂ͓����v��1960�N��K�p���A���[���b�p�̓s�s�ĊJ���̕����x�������̂ł��B�����v��1960�N�́A�O�O�ɐl��������s�s�@�\�̕ω��͂��A���s�S�ɃI�[�K�j�b�N�ɉ^������V���ȑ�2�s�S�̌��݂�����v�Ɛ������Ă��܂����B
�@���z�Ƃ̃s�[�^�[�E�N�b�N�����u�����v��͎����e�����܂����A����́A���{�̌��z��Ǐ]�҂Ƃ��Ăł͂Ȃ��w���҂ւƏ��i�������v���W�F�N�g�ł��Ɛ�^�ł����B
�@�O���搶�ɂ�铌���v��̎�@���A���̌����̕����v��ɖ𗧂��낤���B����͖�O���̎��ɂ͐����A�����������܂���B���������v���������Ă����ߒ��ʼn����V�����q���g����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���܂��B�݂Ȃ���́A�ǂ����l���ł��傤���B�ǂ����A���݂̂Ȃ����ӌ������������肦��K���ł��B
�������v��1960
http://www.tangeweb.com/detail_pdf.php?id=8
���O�����O��
1913�|2005���a-��������̌��z�ƁB�吳2�N9��4�����܂�B�L�����a�L�O�����Ȃǂ̋��Z�v�ɓ��I��������,�n�ʂ��m���B���a36�N�O�����O�E�s�s�E���z�v���������J�݁B38-49�N���勳���B�����{���\���錚�z�Ƃ̂ЂƂ�B��i�ɓ�����X�̍��������������Z��,�����J�e�h�������}���A�吹��,�����s�V���ɂȂǁB���[�S�X���r�A�̃X�R�s�G�Č��s�s�v��,�C�^���A�̃{���[�j���̓s�s�v��Ȃǂ��肪����B55�N�����M�́B62�N�v���b�J�[�܁B����17�N3��22�������B91�B���Q���o�g�B������呲�B