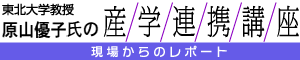
第19回 「オープンである」とは?
「オープンである」と言われると、皆様は何を思い浮かべますか?
安倍内閣総理大臣所信表明演説の「オープンな姿勢」(*i)、Free Trade Area (FTA)の議論(*ii)、それともリナックスに代表されるソフトウェアのオープン・ソース(*iii)、あるいは「オープン・サイエンス」を掲げるサイエンス・コモンズ (*iv)でしょうか?「オープン論」も様々ありますが、今回は、マインド・セットの視点から「オープンである」ということを掘り下げてみたいと思います。
数学の位相空間論(*v)を引用すると、ある集合が「開」であるということは、その補集合が「閉」であることになります。そこで、「閉集合とは?」となりますが、距離空間を例に取ると、「部分集合Aが閉集合である」とは「Aの要素からなる収束する点列の極限がすべてAに含まれる」と定義することができます。クリティカルなのは、閉集合が、補集合との境界を自の要素として持っているという点です。数学者からお叱りを受けるかもしれませんが、この定義を拡大解釈すると、閉じた集合の中でいくら道を開拓しても、所詮行き着くところはその集合の中、となりますでしょうか。
さて、前置きはこのくらいにして、そろそろ本題に入ることにしましょう。「閉じた世界」に身を置くということは、発想がその中で完結してしまうという制限を受けることになりますが、その反面、城壁により、ある種の安心感、安定感が補償されているわけで、いざ「オープンな世界」に変革させようとしても、失うものに先に目が行ってしまうのではないでしょうか。
長年城壁で身を守られて生活していると、それが取り壊され身軽に行動できるようになった時の自分を想像することがなかなかできなくなってしまいます。その逆に、見えないものに対する想像は膨らみます。無防備では、四方から敵が攻撃をしかけ、土足で踏み込んでくる、という強迫観念が働き、侵入者に対する恐れ、未知の空間に対する不安から、防御の壁は更に頑強なものになっていきます。
そこで「どのようにこの負のスパイラスから脱するか?」という課題が出てきます。城壁を壊したからといって、直ちにその集合のアイデンティティ、特性が消えてしまうものではない、という認識を持つことがカギとなります。では「その認識に至るには?」となるわけですが、前提条件とも言えるのが、「個の確立」でしょうか。自分が自分であることを恐れず、素顔の自分を見る、「素顔のままで」自らを取り巻く環境と向き合い、まわりとのインターアクションの中で、育っていく自分を発見するというプロセス(*vi)です。ここで言う「個の確立」とは、「世間一般の理想像に自らをはめ込む」ことではなく、「主体として自らが存在する」ことであり、また「常に進行中」のものである、とご理解ください。
こういった下準備を日ごろから心がけていれば、城壁が無くなったとき、その環境の変化を逆手にとり、これまでの境界に捉われることなく、外部のStimulusを原動力として、発想の転換、新たなアイデアの醸造が可能になります。また、この境界を越えたやり取りにより、時間をかけて培かっていくアイデンティティに更に磨きがかかること請け合いです。「オープンである」ことにより、内に秘められた力と外へと向かう力が共鳴していくのではないでしょうか。
いつの間にか皆様を抽象的な世界に引きずり込んでしまいましたが、ここからは、大学を例に、「オープンである」ことを議論することにいたしましょう。
大学における部分集合とは、学問体系をベースとする「専門分野」となります。上述の定義に照らし合わせてみますと、「専門分野」はどちらかというと「閉集合」になじむような気がします。そこで「研究者が、自らの専門分野を閉集合から開集合に変革させるには何をすれば良いか?」となりますが、大それたことをする必要はまったく無いのです。ただ「専門性」という名の鎧兜を脱衣して、外にインスピレーションを求め、自らの創造性を刺激すれば良いのです。専門分野の中のStimulusにのみ創造性を発揮するのではなく、外の専門分野をもインスピレーションの源泉として使っていくという発想です。
次に視点を変えて「産学連携」を例にした場合、「オープンである」とは何を意味するのでしょうか?これまで、大学の持つ「知」を産業界が活用するという「技術移転型」の産学連携、産業界がかかえる問題を大学人がいっしょに考えるという「問題解決型」の産学連携を通じて、「産」と「学」は、それぞれの守備範囲を踏まえつつ、協力関係を構築してきたわけで、「象牙の塔」に象徴される大学の城壁は低くなりつつあります。であれば「いまさらオープン化なんて!」という皆様の声が聞こえてきますが、ここでは、ちょっと異なる視点から「オープンである」ことを提唱します。
目指すは「社会創造型」の産学連携です。わくわくするような2025年の社会をイメージする。そして、「産」と「学」の協同作業で、それを実現可能にする知とは何かを探ってみる。技術的な側面のみならず、システム、制度、価値観も含めて知恵を絞り、そして行動する。未来社会をデザインする産学連携とでも申しましょうか。
これは創造性を総動員しなければならない作業であり、誰かに任せっぱなしではできません。中央政府がすべてを計画するという時代はソビエト連邦の崩壊ですでに終結しているのです。また未来社会のデザインは「産学」に閉じた話では無く、「実社会」とのインターアクションがあってこそ質の高いものとなるのです。産学連携が「オープンである」所以です。
そこで「まず何から着手する?」となりますが、すべては一国の構成要素である個々のひとの認識から始まると思います。理想は「全員参加型」です。非現実的とお考えですか?そのようなことを考える時間は無いとおっしゃいますか?でも「試してみないことには!」というのが私のスタンスです。例えば、長いリストですが「夫婦のあり方、親子のあり方、家族のあり方、消費者・労働者・生産者のあり方、地域社会との関わり方、地方政府・中央政府との関わり方、世界との関わり方」など、大掛かりな公開討論とは別の次元で、様々な場―例えば、朝目覚めたとき、通勤の電車の中で、バスを待っている間に、アイロンをかけながら、お風呂に入りながら―を活用して、数分でよいのです、考えてみませんか?そして、地域の一員・一国の一員・地球人であること、要は、社会人(「社会」の中の「人」)であることを再確認した上で、日常生活の中で、どこかの片隅に追いやられていた創造性の芽を再度呼び起こしてみませんか?
*i. http://www.kantei.go.jp/jp/abespeech/2006/09/29syosin.html参照。
*ii.http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/index.html参照。
*iii.http://www.opensource.org/参照。
*iv.http://sciencecommons.org/参照。
*v.少し横道にそれますが、N. Bourbakiの"Elements d'histoire des mathematiques"の和訳「ブルバキ数学史」を秋の夜長の友にお勧めします。
*vi.これまたノスタルジアから、ジュネーブ大学で教鞭を取った発生的認知論のJean Piagetの書をお勧めします。
|
