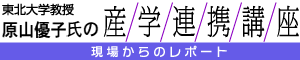
第11回 これからの産学連携
年初めに第10回の原稿をDNDの事務局に送ってからすでに半年が過ぎてしまいました。言い訳がましくなりますが、この間、産学連携に関してはいろいろな側面から考えつつもアイデアを整理する時間がありませんでした。今日は意を決して、「これからの産学連携」を皆様と模索することにいたします。「産学連携」に関してはすでに言い尽くされている、とおっしゃる方も多いと思いますが、ここには「産学連携は時と共に進化する」という考え方が根底にあり、更なる展開を目指すには時折過去を振り返って概念整理を行うことが必要だと実感するからです。まずは現状把握の作業から始めることにします。
●産学連携の現状
科学技術基本法の施行からすでに10年が経過したわけですが、「産学協同」にバトンタッチをしてランナーとなった「産学連携」は、大学等技術移転促進法(通称TLO法)を始めとする制度整備を追い風として、絶え間無く加速を続けてきました。一連の制度改革と共に社会的認識を獲得したわけですが、それと同時に守備範囲も「大学から産業界への技術移転」から「大学発ベンチャーのインキュベーション」、「人材育成」へと広がっていきました。地域共同研究センター、TLO、知的財産本部、大学連携型インキュベータ、インターンシップ、MOTプログラム、専門職大学院、など様々な受け皿が共存するようになり、時には競合的な関係すら見受けられるようになりました。何らかの形でこれらの基盤が有機的に結び付き、それがクラスター形成への第一歩となるのでは、とひそかに期待するのは私一人でしょうか。「知的クラスター創成事業」、「産業クラスター計画」といった中央政府の施策を活用して地域にシナプスを形成していくことも考えられますが、その前提となるのが地域のアクターが主体となって描きだす地域のビジョン―経済活動のみならず社会・文化といった側面も包括する―の存在だと思います。
「産学連携」の牽引役も政府から徐々に当事者である「学」と「産」へと移行しつつあります。また、アクターとしては「公」「民」の参画もちらほら見うけられるようになってきました。例えば、小・中学校で「働く」という社会的なアクトを生徒に考えさせるという動きがありますが、その中で、「アントレプルナーシップ」という価値観に接する機会をソシアル・アントレプルナーとして活躍する企業家・大学人・地域の人々・教員が協働で企画するといったケースです。
イノベーションを社会に誘導する術として登場した「産学連携」ですが、社会制度そのものにも変革をもたらすツールなのではないかと考えるようになってきました。「進化」と称する所以です。
● 産学連携の影には
私達は日々社会において様々な活動を営んでいるわけですが、想定した目的を達成すべくアクションを取る際に負の外部性が生じることが多々あります。「産学連携」も例外ではありません。ここでは、光の部分と表合わせに存在する影の部分に注目することにします。
従来、大学の教員は公的な立場から教育・研究活動を遂行してきたわけですが、「産学連携」を実践する際には、産業という視点を自らの価値体系の中に取り込むことが要求されます。そこで直面するのが、活動の軸足をPublic domainとPrivate domainのどちらに置くか、また主軸と副軸のバランスをどのように保っていくか、等の問題です。
「学術目的で行った研究の成果が商業化を目的とする企業に技術移転される」という稀なケースでは、大学の教員にとって「産学連携」はあくまでも派生効果であり、自らの存在意義をゆさぶることにはなりませんが、「産学連携」とは本質的に大学の教員如いては大学をコンフリクトな状況に追いやるものなのです。「利益相反」、「責務相反」、「不実施補償」、「試験研究の例外」の議論もここに収束します。「産業界への貢献」を真剣に考えれば考えるほど、避け難くなるというのもこの問題の特徴で、しかもそこには一意的な解は存在しないというやっかいなものです。
そこで、「大学及び大学の教員は何を行動規範のよりどころとすれば良いのか?」ということになります。「産学連携」のエキスパートとも言える米国においては、大学に対する及び大学による知的財産権をめぐる訴訟の増加、企業と大学の関係の硬直化、大学院生に対する研究指導の枠の不透明化、といった形でこの問題はすでに表面化しています。「リサーチ・ポリシー」、「産学連携ポリシー」、「利益相反ポリシー」等を設け、行動規範のルールをフォーマルな形で学内外に知らしめることが一般的に行われていますが、これらの基本的な考え方に則って、個々のケースにフレキシブルに対応しているというのが現状のようです。「相反」となる状況を回避する手立てもいくつか取られています。その例が、週一日を学外のコンサルティング活動に充てることを公認する「1/5のルール」(注1)であり、エフォート制、休暇制度であるわけです。また、これまでの「産学連携」の体験をベースに方向性の修正もなされています。カリフォルニア大学においては、1997年に「President’s retreat」 (注2)を行い、学内・産業界の代表を交えて「大学と産業界の関係」の再考を試みました。その結果は、既存のルールの見直し、提言という形でフィードバックされ、フォローアップの作業も1998年以降4回にわたって行われました。「産」と「学」がCandidに協働して「産学連携」の方向性を模索するというスタンスがうかがえます。
● 進路の模索
通常「現状の把握」、「問題点の指摘」の次に来るのが「将来像」となりますが、米国が歩んできた道が示唆するように、「産学連携」は一つの安定した均衡にではなく、動的均衡に収束していくように思えます。またそれを可能にするのが、社会に対するトラストと研究者倫理を持ち合わせた大学人とソシアル・アントレプルナーとしての認識を持つ企業人が繰り広げるインターアクションであり、そこから生み出される新たな知識、技術、価値観なのです。今後の流れとして、「産学連携」は「技術イノベーション」から「社会イノベーション」へとその守備範囲を広げていくのではないかと考えます。
さて、皆様はどのような進路を予測なさいますか?
(注1)Etzkowitz, H. (2002), MIT and the Rise of Entrepreneurial Science, Routledge。
(注2) http://www.ucop.edu/ott/retreat/tabofcon.html参照。
|
