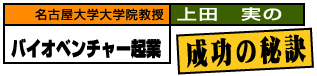
第9回 ベンチャーの難しさと楽しさ
ベンチャーを起業するに際して必要なものは、一般にヒト、カネ、モノだという。ヒトとはまさに起業の主体になって働く人間である。私の場合、臓器工学研究会という勉強会を通じてJTECの大須賀さんや半田さんと知り合った。あくまで偶然の出会いである。オステオジェネシスの親会社の数納さんや西田さんはいまでは信じがたいことだが向こうから研究室に尋ねてこられたのである。なんと幸運なことだろう。というのも現在数多くの大学発ベンチャーが生まれているが、当事者に聞くと一番苦労するのはやはり、中心になって働いてくれる人を見つけることだという。
次にカネ。これはいうまでもなく起業するときの資本金、初期の活動資金のことだ。JTECの場合は親会社の二デックが資金調達の主力になり、先回紹介した医薬品機構の融資にも成功したのも大きな幸運だった。オステオジェネシス社の場合、資本金は1000万円。大半はMBLベンチャーキャオピタルが負担した。親会社は医学生物学研究所である。だから両社とも起業時の資金調達に大きな苦労はしていない。
トップの決断力がすべてポジテイブだったからだ。そして最後にモノとは、ベンチャーの場合、技術シーズと考えてよい。ベンチャーの唯一の財産はシーズ技術の独創性、実用性、可能性である。当然、特許化されていなくてはならない。
私たちがめざした再生医療ベンチャーの場合、基本特許となる細胞の培養方法はいずれも昔から行なわれている方法だったので、特許がないかすでに権利期限が過ぎていた。そこでその細胞をつかっていかにして特定の組織、臓器を効率的につくるのかという点が重要で勝負の分かれ目になる。
われわれは培養表皮をつくるとき、口腔粘膜を材料にすることで、皮膚表皮よりも短時間で、角化しにくい表皮シートがつくれることを発見した。この方法がわれわれの独自技術である。また培養骨の場合、骨芽細胞に血小板を加えることで骨再生が出来る方法をみつけていた。いまから思えばどちらも些細な発明だが臨床的には非常に価値のある発明と言ってよいものである。
こうして、われわれが開発した技術は偶然の出会いと幸運に助けられ、幸先のよいようスタートをきった。これは他の再生医療ベンチャーよりもわれわれが半歩は先んじてスタートしていたということが大きい。なぜ半歩先んじることができたのかはよくわからない。研究という観点からみても、JTECやオステオジェネシスがまだ準備段階だったころ、皮膚、骨の分野で私たちのグループよりはるかに先行していた研究者が何人もいたのである。
それでも彼らはベンチャーを立ち上げなかった。あるいは立ち上げられなかった。それどころか、私がベンチャーを立ち上げる計画を打ち明けると、「そんなことできるはずがない。日本の企業の連中は保守的なので再生医療のような未知の分野にお金を出すはずがない」と、言下に否定されたものだった。
また人工皮膚の研究でわれわれよりも先に企業化をねらっていたある研究者の怒りはすさまじかった。JTECに医薬品機構から融資がきまったとき、新聞がその決定を報じた。たまたま、その日私とくだんの研究者は厚生労働省の一室で会議中であった。たしか培養皮膚の安全性基準について議論をしていたと思う。
そのとき机上の新聞に研究者の目がいった。幸いにも記事の中に私の名前はなかったのだと思う。その結果、かれの怒りは同席していた厚生労働省の人に向けられた。「安全性を議論している最中に、培養皮膚事業に融資するとは何事か!」「この会社にはあなたが協力をしているのか!」と怒号した。若い厚労省係長は震え上がった。私も真相がばれやしないかと内心戦々恐々としていた。若い官僚はあまりの剣幕にもごもごとあいまいな弁解を繰り返し、それでも研究者の怒りはおさまらず、折角何人もの委員があつまっていたのにもかかわらず、その日の会議はおながれになってしまった。
ともあれベンチャーの立ち上げに参画したことによって自分のなかで、明らかにこれまでとは違うやりがいが生まれたことは事実である。研究が研究としてだけで終わらず社会の役に立つ可能性が見えたからである。これまで大学人が行なってきた研究の価値は、専門家の集団である学会が評価するものであった。しかし、ベンチャーをつくるということは一般社会にその研究の価値を委ねることである。桁違いに大きな集団、普遍性のある評価にさらされるのである。成功したときの手ごたえは学会活動からは絶対に得られない強いものである。
また価値観、文化のことなる企業の人たちとの付き合いを通じて、これまで自分が漠然と信じていた「自分というも」のが、意外にちがっていて、全く別の人格や、能力や、志向があることを発見することも楽しいことだった。大学の人間や患者さんとだけ接していれるだけだと、生涯わからなかったかもしれない自分をみつけることができたのは貴重な経験だった。
また自分のなかにある常識というものもいかにあいまいであてにならないものなのかということもわかった。われわれの多くは、ごく狭い限られた人たちとの交流と、繰り返される日常生活のなかから経験したことを普遍のものとして常識化していく。しかし実際は、ある事柄に対する価値観やある人物にたいする評価などは、別の角度からみるとまったく違った結果になることも多いのである。「これはこういうものだ」とか、「あいつはああいうやつだ」、「自分はこういう人間だ」という評価は案外的外れで、全くちがった考え方も出来るということを学んだのもベンチャー活動の成果だったのかもしれない。

▲オステオジェネシス北川氏(左)と筆者
|
<BACK>
|
