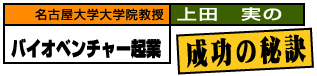
第7回 パートナーはワンマン社長がよい
先回はジャパンテイッシュエンジニアリング社の小沢社長との出会いについて書いた。いわゆる産学連携によって大学発ベンチャーを作るにしても、一番肝心なのは「誰と組むか」ということだ。パートナーのよしあしによって、折角の発明も埋もれたままになって世に出ることはない。そういった意味では、私の場合、パートナーには恵まれた。
JTECの小沢社長はいうまでもなく取締役の大須賀さん、半田さんには戦友に向けるような熱い思いがある。オステオジェネシス社の北川前社長、加登住さんとは話しているうちに、次第に熱くなりやがて口論に近い議論のはてに、深い絆をつくることができたのは幸いだった。医学生物学研究所の数納会長、西田社長はわれわれの熱い戦いを包容力ある態度で見守っていただいた。
こうした議論はなにがテーマだったのか今となっては覚えていない。それほどにささいな問題だったのだろう。ではなぜこうまで熱い議論になるのか、それはお互いの仕事における最優先事項が違うからだ。研究者は自分の仕事が何よりも大事で誇りもある。ところがビジネスの世界では別の価値尺度があり、ときに研究者の誇りが傷つくのである。企業の論理と大学の文化が激突するのだから、それは激しいエネルギーである。ただ私の場合、相手の忍耐力に救われて今日まで来ることができた。
今にして思うのは、研究者は自分の価値観に拘泥せず、企業側のひとが魅力を感じ、可能性を信じられる説得力、説明力がなくてはならない。また企業側のひとは、弱く傷つきやすい(?)研究者の努力を認めることからはじめてほしい。とはいうものの最後の決断は企業のトップがするのだから、自分の技術を売り込もうとする研究者は、中間管理職とは会わず、できるだけ早くトップに会えるように働きかけることが大事だ。とくに大きな企業ほど、間にはいる人間が多くなり、人から人に案件が伝えられるたびに、研究者の伝えたい情熱はさめ、伝言ゲームのごとく全く別の話になってトップに伝わるのである。
こうして到達した研究者の情熱も最終決断者の社長が、サラリーマン的ではたいていうまくいかない。結局は前例主義の官僚的判断になってしまう。新しいことをやろうとしているのだから、前例などないのだから、研究者の情熱と可能性に賭けられる決断力をもった社長を交渉相手にすべきだ。サラリーマン社長にはこうした力はなく、たいていは周囲から恐れられるワンマン社長かオーナー社長しかこれはできない。

▲小沢社長(右)と会話をする筆者
|
<BACK>
|
